
八王子 文学碑
芭蕉句碑

明治三十六年(1903)に
当寺の第三世寛誉泰道大和尚によって建立されたものである。
全文
当寺の第三世寛誉泰道大和尚によって建立されたものである。
碑右側面明治三十六歳次発卯九月建
発願人 正風水音八王子分社長 蚯庵主 高味石田
碑左側面獅子門十七世 千秋菴敬書
碑 形 根府川石 高さ4尺3寸 幅2尺 厚さ一尺
句表
句は、「笈日記「泊船集」「蕉翁句集」(貞享5年とする)に収録されており、いずれも「画賛」と題している。おそらく松を画いた絵に賛を望まれた折の 吟と思われる。露のしたたりそうなみずみずしい松が立っている、この松の木かげに西行が立ち寄り、長旅ですですり切れた草鞋などがかかっていたら一層 風情があるものを、の意である。
なお「栢の露」は「松の露」が正しい。
寺内にある「西行塚」に因んで西行を敬慕した芭蕉の句碑の建立が企画さ れたものであろう。
主監の「瀧見可屋」は当時の先々代の住職で三世寛誉泰道大和尚・俗名 瀧見泰道で、俳句に熱心で八王子を代表する近代俳壇を代表するひとりであり、寺内に
「涼しさや月下にならす花鋏」の句碑があり、又八王子鑓水の永泉寺境内にも「しばらくは夢のかりきるはな衣」の句碑が建っている。
碑表の文字の執筆者「千秋庵」は「新選俳諧年表」(大正十二年刊)の大正八年の頃にみえる。
「 鶴汀歿、二月十一日、享年八十六、塩谷氏、名新吉、千秋庵瑞夢仙と号す。美濃人」と同一人物と考えられている。又「獅子門」とは美濃派とも言い
蕉門十哲の一人各務支考の一派である。
八王子市内の芭蕉句碑はこの他「ひばりより上にやすら小峠かな」(天保十一年建立、浅川老人ホーム内)「先たのむ椎の木もあり夏木立」(明治四十 三年)建立、鑓水 永泉寺境内)「しばらくは花の上なる月夜かな」(建立年次不明、下恩方辺名)「蝶の飛ぶばかり野中の日かげかな」(昭和二十四 再建、新町の永福稲荷)などが知られている。
八王子市内の芭蕉句碑はこの他「ひばりより上にやすら小峠かな」(天保十一年建立、浅川老人ホーム内)「先たのむ椎の木もあり夏木立」(明治四十 三年)建立、鑓水 永泉寺境内)「しばらくは花の上なる月夜かな」(建立年次不明、下恩方辺名)「蝶の飛ぶばかり野中の日かげかな」(昭和二十四 再建、新町の永福稲荷)などが知られている。
文責 大東文化大学 文学部教授 萩原 恭男
昭和五十九年甲子十一月
清凉山 長心寺
西行塚

碑面の字は、平安以来代々蹴鞠・和歌を業とし、書道にも一派を成した
飛烏井家の人によって書かれたものであるが、年代は不明である。
可屋句碑

可屋は、当寺第三世寛誉泰道大和尚・俗名瀧見泰道で、八王子の近代俳壇を代表する一人として知る人も多い。
ちなみに、八王子市鑓水の永泉寺にも可屋の「しばらくは 夢のかりきる はな衣」の句碑がある。
信仰を集めた「甲子大黒天」
 台所の守護神として、又福神として広く信仰されている大黒天は、古代インドではマハーカーラ(偉大な黒い者)、訳して大黒天神といった。これが仏教に採り入れられ、我が国では平安末、厨房を守る神として寺院の庫裡に祭る風が生じた。
台所の守護神として、又福神として広く信仰されている大黒天は、古代インドではマハーカーラ(偉大な黒い者)、訳して大黒天神といった。これが仏教に採り入れられ、我が国では平安末、厨房を守る神として寺院の庫裡に祭る風が生じた。
また大黒と大国とが音通であるところから、大黒と大国主が習合され、福袋を肩に打出の小槌を持ち米俵を踏まえる姿も一般的になた。大黒天信仰は鎌倉から室町時代にかけて民間に広まり、江戸時代には特に商家で七福神のひとつとして流布した。大国主との関連から子の神とも習合して鼠をその使いとし、甲子の晩に大黒講を催す風習も生まれた。
本寺の大黒天石像は、寛文元年(1661)に北海長老が堂宇を再興した折、特に江戸の石工に彫らせ、「力士雷電ヲシテ遷座」と伝えられたもので、六十日に一度の甲子の日に縁日が開かれ賑わいを見せていたが、戦災により座像が焼失してしまった。
現在の三俵大黒天は、昭和三十年(1955)、台町の宮崎勝五郎氏の寄進によるもので、佛師佐藤光重氏の作である。
史 跡
広徳館跡
−自由民権運動の活動拠点ー
明治十一年(1878)末、藩閥政治に対坑して、人民の自由と権利の伸長を唱え、政治への参加を要求する自由民権運動がおこり各地に広がった。 同十四年(1881)には、板垣退助を総理とし、「自由民権の拡張、立憲政体の樹立」を綱領とした自由党が結党された。同十六年、八王子でも有志が共立会を設立し、十二月に境内地にあった蟠龍館(木造2階建て)に「広徳館」を開設し、 ここを自由党の根拠地として、館主林副重を中心に活動を展開した。
明治十一年(1878)末、藩閥政治に対坑して、人民の自由と権利の伸長を唱え、政治への参加を要求する自由民権運動がおこり各地に広がった。 同十四年(1881)には、板垣退助を総理とし、「自由民権の拡張、立憲政体の樹立」を綱領とした自由党が結党された。同十六年、八王子でも有志が共立会を設立し、十二月に境内地にあった蟠龍館(木造2階建て)に「広徳館」を開設し、 ここを自由党の根拠地として、館主林副重を中心に活動を展開した。
景活を賞された長心寺
『八王子繁昌誌』(明治二十三年・1890)所収の澳津涯江作「八王子八勝起」中に、「鵯山遠望」「玉衝山月」「百樹園花」「桑田暁靄」「舟森水樓」「霽岡湧水」「麻川蛍火」についで、次の一説がある。
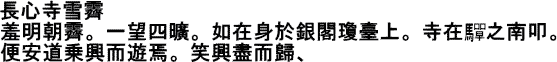
(大意)夜の間降った雪も、朝になってすっかり晴れ上がった。
銀一色となって広がった四方の隅々まで、一目で見渡すことができる。この身は、かの銀閣寺の美しい楼閣に立っているように感じられる。寺は、八王子駅の南にある。そこでゆっくりと歩を進め、雪の降り積った道の面白さにまかせて、あてどもなくさまようのである。
雪景色の美しさに顔はほころび、興の尽きたところで帰るのである。
現在は市街化され、昔の景観は残念ながら残っていないが、今も閑静なところである。